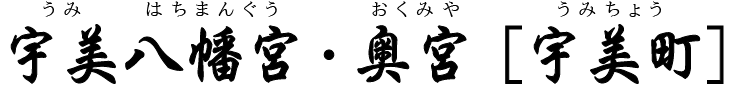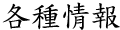胞衣ヶ浦は、境内から後方、北東250m程にある小山に鎮座する宇美八幡宮の奥宮です。
糟屋郡宇美町に鎮座する宇美八幡宮は、三韓征伐より御帰還された神功皇后が、應神天皇を安産にて御産みになられた地です。産所を蚊田邑(蚊田は宇美の古名)に定めた神功皇后は、側に生出づる槐の木の枝に取りすがって、軽い御産で應神天皇を御産みになったと伝えられ、この産所を名づけて「宇瀰」。その後に「宇美」と称されました。御産所の四辺に八つの幡を立てて兵士に守らせた故事が後世、八幡大神と称する由縁となったとも伝えられています。
應神天皇を御産みになった神功皇后は、胞衣を産所の北に流れる宇美川で洗い濯ぎ、筥に入れて、奥宮とされる北東250m程にある小山に奉安したとされています。そのため奥宮は、胞衣ヶ浦とも称されています。
『日本書紀』巻第十 譽田天皇(應神天皇)
譽田天皇、足仲彦天皇第四子也、母曰氣長足姫尊。天皇、以皇后討新羅之年、歲次庚辰冬十二月、生於筑紫之蚊田。幼而聰達、玄監深遠、動容進止、聖表有異焉。
誉田天皇は、足仲彦天皇の第四子なり。母をば気長足姫尊と曰す。天皇、皇后の新羅を討ちたまひし年、歲次庚辰の冬十二月を以て、筑紫の蚊田に生れませり。還り給う十二月十四日誉田天皇(応神天皇)を筑紫に生み給う。幼くして聡達くいます。玄に監すこと深く遠し。動容進止あり。聖表異しきこと有り。
『古事記』中巻 神功皇后
故其政未竟之間 其懷妊臨產。卽爲鎭御腹取石以纒御裳之腰而。渡筑紫國其御子者阿禮坐。故 號其御子生地謂宇美也。亦所纒其御裳之石者在筑紫國之伊斗村也。
故、其の政未だ竟へざりし間に、其の懐妊みたまふが産れまさむとしき。即ち御腹を鎮めたまはむと為て、石を取り御裳の腰に纒かして、筑紫国に渡りまして、其の御子は阿礼坐しつ。故、其の御子の生れましし地を号けて宇美と謂ふ。亦其の御裳に纒きたまひし石は、筑紫国の伊斗村に在り。
宇美八幡宮は、敏達天皇の御代(572-585)宮柱太敷き建て、八幡大神御降誕の聖地として神功皇后と應神天皇の母子神をお祀りし、後世に至り玉依姫命、住吉大神、伊弉諾尊も合祀し五柱としてお祀りされました。
旧暦の12月14日に應神天皇の御生誕を祝う「御誕生祭」を斎行していましたが、現在は12月14日に「胞衣ヶ浦祭」を、1月15日に「御誕生祭」を斎行しています。
また、宇美八幡宮の奥宮(胞衣ヶ浦)と共に、胞衣を祀るとされる伝承地が筥崎宮です。筥崎宮では、筥に歛めた胞衣を、白砂青松の葦津ヶ浦に御埋鎮し、御標として松を植えたと伝えています。「標の松」は「筥松」と名付けられて以後、筥松のある岬(崎)ということで「筥崎」の名が起こったと伝わっています筥崎宮では新暦12月14日に「御降誕祭」が斎行されています。