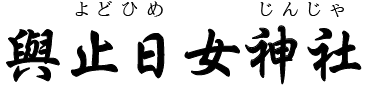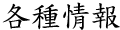河上神社、淀姫さんとも称される與止日女神社は、『延喜式神名帳』に「與止日女神社」と見える式内小社、及び肥前国一宮です。
文亀3年(1503)吉田兼俱による『延喜式神名帳頭註』の『肥前国風土記』逸文によれば、欽明天皇25年(564)11月1日に與止姫神が鎮座したとされています。御祭神の與止日女命は、神功皇后の妹で八幡大神(応神天皇)の叔母であると伝えています。
『延喜式神名帳頭註』
與止日女。
風土記云、人皇卅代欽明廾五年甲申冬十一月朔日甲子、肥前国佐嘉郡與止姫神有。一名豊姫、一名淀姫。乾元二年記云、淀姫大明神者、八幡宗庿叔母神功皇后之妹也。三韓征伐之昔者、得于滿滿两顆、而没異域之凶徒於海底。文永弘安之今者、旋風雨之神變、而摧幾多之賊船於波濤云云。河上大明神是也。
與止日女。
風土記云はく、人皇三十代欽明二十五年甲申の冬十一月朔日甲子、肥前国佐嘉郡に與止姫神有り。一名を豊姫といい、一名を淀姫といふ。乾元二年記云ふ、淀姫大明神は八幡宗廟の叔母、神功皇后の妹なり。三韓征伐の昔に、于滿々の両粒(満珠干珠)を得て、異域の凶徒を海底に没せしむ。文永弘安の今は、旋風雨の神に変わりて、幾多の賊船を波濤に摧けしむ云々。河上大明神、是なり。
また、『肥前国風土記』では嘉瀬川(佐嘉川)の川上に世田姫という名の神が石神で祀られており、毎年、鰐魚(小さいサメ)の姿をした海神では、小さい魚を伴って遡上して石神を詣で、数日留まった後に海へ還ると伝えています。また、その魚を取って食べると死ぬこともあるとされ、今も御祭神の眷族とされるナマズを食べない習俗は、その名残と考えられています。
『肥前国風土記』
佐嘉郡。…(略)…。云郡西有川。名曰佐嘉川。年魚有之。其源出郡北山南流入海。(略)又、此川上有石神。名曰世田姫。海神で年常、逆流潜上、到此神所、海底小魚、多相従之。或、人畏其魚者、無殃。或、人捕食者、有死。凡此魚等、住二三日、還而入海。
佐嘉の郡。…(略)…。云はく、郡の西に川あり。名を佐嘉川と曰ふ。年魚あり。其の源は郡の北の山より出て、南に流れて海に入る。(略)又、此の川上に石神ありき。名をば世田姫と曰ふ。海の神年常に(鰐魚を謂ふ)流れに逆ひて潜り上り、此の神の所に到るときに、海の底の小さき魚、多に相ひ従ふ。或いは、人其の魚を畏まば殃いなし。或いは、人捕り食はば、死ぬること有り。凡そ此の魚等、二三日住まり、還りて海に入る。

神社の北1.7km程には、天地万物を作った造化大明神が、金敷城山の中腹に奉斎されています。與止日女神社上宮とされ、男神石・女神石からなる御神体の三面の大石は、二面が壁として立ち、一面がその上に蓋する形になっています。古来より土人石神と称して、明治の中頃まで11月20日に祭事が執行されていました。與止・世止・世田との言葉の近しさから、世田姫を鎮祭しているとされています。中は洞窟になっており、通り抜けることもできます。(地図)
朝廷の御崇敬篤く、『日本三代實録』では、貞観2年(860)に従五位下、貞観15年(873)に正五位下に昇叙。延長5年(927)編纂の『延喜式』では、式内小社と見ることができます。室町時代編纂の『大日本一宮記』では、神護景雲元年(766)に一宮となったことが記され、少なくとも応保期(1161-1162)には肥前国一宮として定着していたと考えられています。弘長元年(1261)2月20日には、最高位の正一位の神階を授けられました。
『日本三代實録』卷四
貞観二年(860)二月八日己丑。進肥前國從四位下田嶋神階加從四位上。授従五位上荒穗天神正五位下。従五位下豫等比咩天神、久治國神、天山神、志志岐神、温泉神並従五位上。正六位上金立神従五位下。
『日本三代實録』卷二十四
貞観十五年(873)九月十六日戊寅。授肥前國從四位上田嶋神正四位下。従五位上志々神。豫等比神正五位下。
『延喜式神名帳』延長5年(927)編纂
西海道神一百七座[大卅八座・小六十九座]。
…(略)…。肥前國四座[大一座・小三座]。松浦郡二座[大一座・小一座]、田嶋座神社[名神大]、志志伎神社。基肄郡[小]、荒穂神社。佐嘉郡一座[小]、與止日女神社。
『大日本国一宮記』室町時代編纂
一ノ宮佐嘉郡。川上明神淀姫命、大己貴命、事代主神。右三神を祀る。四十八代称徳天皇神護景雲元年(766)、当国へ鎮座の一宮と号す。
肥後国宗祀の主要な地位を占め、5月、8月の神事に際しては、国衙方奉仕の事がありました。
鎌倉時代には、院宣、並びに関東御教書を賜わり、肥前一箇国平均の課役により社殿の造替遷宮を営むのを例としました。元亨2年(1323)後宇多院の院宣並びに幕府の御教書を賜って、本殿以下の造替を行い、同年8月29日に遷御の儀を執行。社領も、付近一帯の地に亙り、仁治年間(1240-1242)には270余町の神佛事料免田を、正応年間(1288-1292)の造営に際しては、13,470余町の造営免田を有するに至りました。
元亀元年(1570)肥前国の龍造寺隆信ととキリシタン大名であった大友宗麟は「今山の戦い」で対峙します。その戦いの舞台となったのが現在の鎮座地周辺であったため、社殿など全て焼き払われましたが、元亀4年(1573)に再建されます。
慶長7年(1602)に後陽成天皇より「大日本国鎮西肥前州大一之鎮守宗廟河上山正一位淀姫大明神一宮」の勅額を賜りました。しかし、慶長7年(1602)に千栗八幡宮も後陽成天皇から「一宮」の勅額を下されていたことから両社の間で紛争が続くこととなります。最終的には延宝7年(1679)11月以降、双方共に新しく「一宮」の記載を許されないことで決着しました。
藩主の鍋島家からも篤く崇敬を受け、文化13年(1816)火災により元亀4年(1573)に再建の西門以外を焼失しますが、鍋島家より再建。社領として田畑350町を保持しました。明治4年12月県社に列格されました。名勝「川上峡」の中心に位置し、神社境内は佐賀市景観重要建造物にも指定されています。
「與止日女天神」
境内の西側(道路寄り)に鎮座。菅原道真公を学問の神として祀っています。
「社殿背後石祠」

社殿背後に16の石祠が並びます。その中の百代宮と代永宮は、それぞれ豊玉姫命の和魂と荒魂を祀っています。若宮神社(仁徳天皇)、香椎社(神功皇后)、竃門神社(真津彦命)、寶満社(玉依姫命)、王子社(大伴別合)、淀姫社(豊玉姫命)、住吉社(海童神)、志賀社(海童神)、加茂社(加茂別雷神)、春日社(天之子屋根命)、稲荷社(倉稲魂神)、阿蘇社(健磐龍命)、山王社(大山咋神)、乙宮社(三女神)、高良社(武内宿禰)。百代宮(豊玉姫命の和魂神)、代永宮(豊玉姫命の荒魂神)。
「金精様」

子孫繁栄のシンボル。境内に入ってすぐ右側に祀られています。神功皇后の三韓征伐の折り、当地に留まった妹神の與止日女命が、子宝に恵まれぬため密かに館の一隅にあった男根の自然石に肌をふれて子宝を願ったところ、色あくまで白く、きめ細やかにして玉の如き子供を授かったと伝えられています。子宝、子孫繁栄の御神徳。
「社殿(本殿・中殿・拝殿)」
現在の社殿は、文化10年(1813)の火災から文化13年(1816)に再建されたものです。本殿は、五間社流造、側面四間。中殿は、正面一間、側面四間。拝殿は、正面五間、側面三間で、入母屋造唐破風付。総べて屋根銅板葺、総素木造、随所に絵様彫刻がなされています。正面、側面の蟇股、破風の懸魚等に室町後期の様式が残されています。
「河上神社文書」
国指定重要文化財。総数247通、14巻の巻物仕立てで、現在は県立図書館で保管されています。平安時代10通、鎌倉時代92通、南北朝時代85通、室町時代57通、安土桃山時代3通からなります。その中最も古いものは、寛治5年(1091)の社増円尋解状です。これに続く永久2年(1114)の白河上皇の院庁下文は、この種様式の文書としては国内でも最古のものに属します。中でも南北朝関係文書は、14世紀の九州の動向を示す史料として貴重とされています。昭和55年(1980)6月6日、国重要文化財に指定されました。
「西門」
元亀元年(1570)のキリシタン大名であった大友宗麟の焼き討ちの後、元亀4年(1573)の造立。文化10年(1813)火災から残った唯一の建造物です。昭和61年(1986)3月19日、佐賀県指定重要文化財に指定されました。
「三の鳥居(肥前鳥居)」
石造明神鳥居の三の鳥居は、笠木鼻の形に特有の様式が認められる肥前鳥居です。柱に「慶長十三歳仲秋吉祥日 鍋島信濃守藤原朝臣勝茂」の銘があります。佐賀市指定重要文化財に昭和58年(1983)10月17日指定されました。
「焼楠」
神殿西に残る根株。廻六丈、高三丈六尺、霊木の大楠として名高かったもの、文化10年(1813)の火災のため焼亡。鍋島勝茂が残った根株の四囲に高く石垣を築かれたものが残っています。
「大楠」
境内の入口、鳥居のすぐ後ろにある御神木。樹齢1450年とされています。