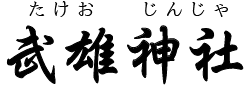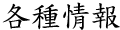武雄神社が鎮座する御船山は、舳先にあたる南嶽(207m)と艫にあたる北嶽からなり、神功皇后が三韓征伐の帰途、武雄に兵船を止め、それが山と化したものとされています。その山麓に鎮座しているのが武雄神社で、御祭神として、武雄大明神(武内宿禰・武雄心命・仲哀天皇・神功皇后・応神天皇)として5柱の神を祀っています。
寛文年間(1661-1673)前後に神主23代の伴信門しが編纂した『武雄神社本紀』によると、創始は年古くして不明ですが、元は御船山の南嶽に鎮座していました。
聖武天皇の御代(724-749)初代宮司の伴行頼に神託があります。
『吾は武内大臣である、昔神功皇后が朝鮮の新羅を征した時、自分もそれに従ったが、御船山の南嶽は住吉神の指揮を執るところであり、その社に私を祀れば、この地に幸福が訪れるであろう。』と。
その神託を受けた伴行頼は、大宰府を通じて朝廷に奏請し、御船山の北麓に神殿を建築。南嶽の頂上には住吉三神(底筒男神・中筒男神・表筒男神)を祀り上宮とし、北麓の神殿に武内宿禰を主祭神とし、仲哀天皇、神功皇后、応神天皇、武内宿禰の父である武雄心命を合祀しました。御船山の艫にあたる北嶽には、武内宿禰の子の平群木兎宿禰を祀り下宮としました。時に天平7年(735)旧暦1月17日であったとされています。後に、朝日町黒尾に黒尾明神を創建して、武内宿禰の母の影媛を祀りました。主祭神である武内宿禰は、政治を補佐する大臣として第12代の景行天皇から第16代の仁徳天皇まで5代の天皇に仕え、実に360歳の長寿の神様として知られています。
平安時代での旧社格は、九州地区の統治組織「大宰府」の府社とされ、祭礼に国使が参向するなど、杵島郡の鎮守としてだけではなく、肥前国の名社として深く重んぜられていました。また、それらを裏付ける218通にもおよぶ古文書が現存しており、九州における神社文書の代表的な遺品とされています。
元永年中(1118-1120)肥前後藤氏2代領主の後藤資茂が、朝夕秀麗な御船山の麓に鎮座する武雄神社を望み、築城の適地と思い、朝廷に奏請して当社を現在地に遷座し、旧社地の北麓には塚崎城が築かれました。
文治元年(1185)の壇ノ浦の戦いでは、源頼朝が当社に密使を使わせ平家追討祈願。平家を滅ぼした源頼朝は、勝利を武雄神社の御神徳によるものと感じ、後鳥羽天皇の勅使として左大弁藤原基氏、源頼朝の名代として天野遠景を赴かせ、文治2年(1186)3月10日の日付で『源頼朝加判平盛時奉書』を御教書を呈し深謝しました。この参詣を歓迎して、武雄四代領主の後藤宗明が流鏑馬を奉納し、今に伝えられています。 また、これを機に武雄神社と源氏との関係は極めて密接となり、神社として将軍家の祈祷に当たる関東御祈祷所の使命と、社家として御家人の使命を有し、二重の立場に於いて活動することになりました。
鎌倉中期の元寇では、未曾有の国難に際し、伏見天皇より異国降伏の祈祷の『綸旨』を賜る光栄に浴し、文永の役(1274)の10月20日の夜、武雄神社の神殿から鏑矢が元軍船目掛けて飛び、元軍は逃げていったとあり、弘安の役(1281)では上宮から紫の幡が元軍船の方に飛び去り、大風を起こしたとあります。この霊験により『九州五社ノ内』と称され、九州の宗社として隆々と栄えた時代もありました。後、鍋島家の領有となっててからも篤く崇敬されました。
現在は武雄の氏神社として、武運長久、開運、厄除けに霊験あらたかな神様として氏子はもとより全国各地から広く信仰を集めています。
【神事・祭事・宝物】
流鏑馬神事
例祭日の10月23日に斎行。寿永3年(1184)源頼朝は、武雄神社に密使を送り平家追討を祈願し、白鷺が源氏を守護して勝利しました。文治2年(1186)源頼朝は御教書を送り戦勝を深謝し、さらに後鳥羽天皇の勅使として左大弁藤原基氏、源頼朝の名代として天野遠景を遣わして戦勝を報告させました。彼らが武雄に着いたのは9月21日で、武雄領主の後藤宗明は、神主の伴守門と23日に武雄神社に参詣し、神事が終わったあと流鏑馬を奉納しました。それが武雄神社の秋祭り(武雄供日)の始まりで、流鏑馬奉納の始まりです。平成7年(1995)11月8日に市重要無形民俗文化財に指定されました。
歩射祭
2月17日に斎行。14時から本殿で神事が執り行われ、裏鬼門(南西)に大的を設け氏子2名による奉射が行われます。『武雄神社本紀』によれば、御船山の南嶽にあった祠を北麓に遷座し、神前に猪牝牡2頭、野兎1羽、鵠鳥2羽をお供えし盛大な遷座祭を行ったと伝えられています。その祭典後は、本殿の鬼門(北東)に大的を設け、宮司が6本奉射したとその起源が記されています。県内最古の神事とされ、五穀豊穣を願うと共に年占いの意味があります。6本の矢を射終わると、神前にお供えした猪肉は天平汁にして参拝者に振る舞われ、兎の毛は御守として授与されます。
武雄神社文書
平安時代中期から室町時代末期にかけての古文書で、昭和54年(1979)6月6日に国指定重要文化財指定。最古のものは、天暦5年(951)2月11日の日付けの四至実験状です。全部を合わせて218通に及び、武雄神社の所領が拡大し、発展する過程を示すものを多く含んでいます。九州における代表的な神社文書です。
【境内社など】

「本殿」
元永年中(1118-1120)の遷宮後、初めて改築されたのは慶長17年(1612)とされています。昭和39(1964)年1月20日の不審火により焼失。しばらく仮殿で祀られていました。昭和45年(1970)12月、銅板葺屋根の鉄筋コンクリートの社殿が再建されました。社殿は、流造の本殿に唐破風付き入母屋造りの拝殿。色は当社の神使とされる白鷺にあやかり、白を基調としています。

「御神木(武雄の大楠)」
社殿前から150m程後方に祀られています。樹齢3000年以上、主幹の幹周20m、根回り26m、高さ27m。環境庁の巨樹・巨木林調査では、全国で7位(楠だと5位)の巨木です。昭和45年(1970)7月15日に武雄市天然記念物に指定。根元の肥大した部分は、12畳もの広さを持った洞となっており、中には天神の石祠が祀られています。

「塩釜神社・城山稲荷神社」
社殿向かって左。御神木の楠への参道入り口に鎮座。塩釜神社と城山稲荷神社を合わせ祀っています。「塩釜さん」と称される塩釜神社は、国土鎮護、商売繫昌、航海安全、安産、延命などの神。天保8年(1837)6月、宮城県塩釜市の総本社に勧請し奉斎されたと伝えらています。城山稲荷神社は、安政5年(1858)9月の勧請。城山は御船山の別名で、倉稲魂神・猿田彦命・大宮女命の三柱神に摂社の田中大神・四大神の二柱神を加え稲荷五社大明神と称し、殖産興業の守護神として祀られています。

「下ノ宮」
本宮の主祭神である武内宿禰の御子神の平群木兎宿禰を祀っています。天平7年(735)武雄神社本宮の遷宮と同時期に、御船山の西北麓の峡に下ノ宮が創建されたと伝えられています。元永年中(1118-1120)に本宮が現在地に遷宮されたのと同時期に塚崎の大楠の場所に移され、その後に現在地に遷宮されたと推測されています。
「荒神社」
夫婦檜の近くに鎮座。「荒神さん」と称される火の神、竃・台所の神。文化13年(1816)8月に奉斎。火の神聖性と畏れの観念が、荒ぶる神の信仰と一体となって成立した民間信仰の神様です。
「鳥居」
第一、第三鳥居は肥前鳥居と称し、その型式が肥前国独特のものであります。
「夫婦檜(むすびの樹)」
2本の檜が根元で結ばれ、樹の中ほどで仲睦まじく立っているかのように再び枝が合着しています。当社の御祭神である仲哀天皇・神功皇后の御神威の顕れとされ、根元は夫婦和合、繋がった枝は様々な縁を繋ぐ縁結びの象徴として信仰されています。
「心字の池」
「心」の草書体の形をしており、例祭日には清祓が執り行われます。壇ノ浦の戦いでは、ここから飛び立った白鷺の群れが、源氏を応援し、励ましたと伝えられ、武雄神社の神使とされています。