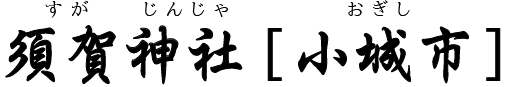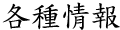標高90mの城山の西に鎮座する須賀神社は、「見事見るには博多の祇園、人を見るには小城の祇園」と称された団扇祇園で知られる神社です。御祭神として健速須佐之男大神と櫛稲田姫大神を祀り、旧社格は県社。祇園川を渡った麓の二の鳥居と神門から高さとしては35m程ではあるもの、一直線に上る急峻な石段が社殿まで繋いでいます。石段の途中の三の鳥居は、肥前鳥居です。社殿前からは、小城市を一望するだけでなく、遠くに雲仙・阿蘇の噴煙を望見できます。
延暦22年(803)の創建と言われ、当初は「清祠」と称し、肥前国の佐賀・杵島・小城三郡の宗廟として栄えたと古記にあります。その後、鎌倉幕府の命により下総国(現・千葉県北部と茨城県西部)より千葉胤貞が下向します。その際、御神体として祀られている木造を刻して山城国祇園社(八坂神社)の御分霊を勧請し「祇園社」となります。その時に山城の千葉城(牛頭城・祇園城)も作られ、今に伝わる祇園会の山挽行事も始められましたといわれ、千葉氏の守護神として代々の城主は懇ろに奉斎しました。
戦国時代、千葉氏は東千葉・西千葉の両家に分かれて争い衰退、祗園川にそって城下町が栄えましたが天文15年(1546)馬場頼周と龍造寺剛忠(家兼)の合戦で城も城下町も焼けてしまいました。代わって当地を領した龍造寺隆信とが社地・社領を寄進。天正18年(1590)に鍋島信昌(直茂)が本殿を再建。天正19年(1591)に拝殿を再建しました。代々の領主からの崇敬篤く、大祭日には各名代をして参拝・奉幣せられ、小城、鹿島、蓮池の三家、及び多久、武雄、その他親類家老も代参がありました。祭事に要する費用は小城藩主より供進せられ、数百人の警固、2000人余りの奉仕人夫を出して、山鉾を引くのを例としたといわれています。
明治6年(1873)村社に列せられ、明治9年(1876)須賀神社と改称。大正13年(1924)に県社に列格されました。厄災消除・家内安全・農商工の産業振興の御神徳のある神として、古来より近郷近在の人々の深い信仰を集めています。
【神事・祭事】
団扇祇園
旧暦6月15日、現在は7月の第四日曜日の例祭日、及びその前夜に行われる団扇祇園は、鎌倉時代に始まった勇壮な山挽行事です。3台の山(山鉾・山笠)が下町から中町を経て、上町の祇園社前広場まで引かれ、再びもとの場所まで引き戻されます。
建武元年(1334)下総国から小城に下向した千葉胤貞が、山城国祇園社(八坂神社)の御分霊を勧請し、祇園会に山挽行事を始めたのが始まりです。当初は、竹・藁・カズラで組み立てられた山鉾(櫓)に乗り、笛と太鼓によって兵に軍陣の駆け引きの訓練をしたものとされています。現在もその伝統に則り、山(山鉾・山笠)には釘を一切使わず、竹・藁・蔓だけで作られています。
疫病退散を祈願する祭りとして受け継がれ、江戸時代、小城藩の創設後は、藩営の山挽神事として「見事見るには博多の祇園、人を見るには小城の祇園」と称される程の賑わいを見せました。藩政時代の山挽神事の形態は、先山と後山(本山)の2台の山鉾が、下町(下河原)から上町(上河原・祇園社前)まで引かれ、再び下まで引き届けるものでした。2台の山鉾にはそれぞれ7~8名の武士が乗り込み、夫役によって駆り出された農民たちが引きました。上河原には山桟敷ができ、藩の重臣出席のもとに能も興行されました。祭事に要する費用は、小城藩主から供進されるだけでなく、数百人の警固、2000人余りの奉仕人夫を出して、山鉾を引くのを例としたと伝えられています。しかし、天保14年(1843)佐賀本藩の厳しい倹約令のため山挽は中止に至ります。明治期になり上町・中町・下町の町民により再興され、各町がそれぞれ山鉾を引くことになり、3台の山鉾・山笠が巡航しています。上町と中町は屋形型の山笠で、下町の山鉾だけが藩政時代の形態を伝えています。
宵祭は、横町による浮立奉納から始まり、翌日に上町・中町・下町の3台の山(山鉾・山笠)が点灯されます。翌日は、10時からの出陣式が終わり次第、「上り山」が斎行されます。その時、山頂の社殿にて神事が行われています。また団扇祇園の他に、厄除開運を祈念する花芝祇園(2月第3日曜日)。五穀豊穣、万事円満を祈念する柿祇園(9月第3日曜日)も執行されています。
【境内社など】
宝貴稲荷神社
社殿向かって右手に鎮座。保食神を祀っています。
階段前右の石祠
神門を過ぎて階段前右に石祠で鎮座。金毘羅社、庚申社(猿田彦命)、大神宮(天照皇大神)などが祀られています。
文殊菩薩
二の鳥居左に鎮座。智慧を司る仏様です。
大楠神社
二の鳥居の向かって右手に勾配のなだらかな裏坂は、尚武の神様として楠木正成を祀る大楠神社の社殿に通じています。その途中にも祠が並んでいます。
天満宮
社殿に向かって左手奥に鎮座。学問の神として菅原道真を祀っています。