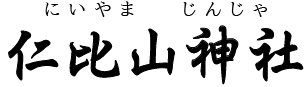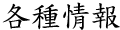地元の人に「山王さん」と呼ばれ親しまれている仁比山神社は、天平元年(729)僧の行基が、聖武天皇の勅願を賜り、神殿を建立して松尾明神を勧請し、国家安泰、五穀豊穣を御祈願されたのが創始です。
承和11年(844)慈覚大師が唐より帰朝の際、国家安泰の祈願の為に御神水を得る時、土中より「日吉宮」の石額を発見したことを朝廷に奏上します。比叡山の神威を感じた時の仁明天皇は勅命を以て、比叡山の日吉山王宮(日吉大社)の分霊を合祀し、朝廷の祈願所と定めました。その時、仁明天皇の「仁」と比叡山の「比山」を併せて「仁比山」と名付けられました。一般に「仁比山」は、「にいやま」と読まれていますが、本来は、この「にひやま」が正式で、地元では「にーやま」と称されています。
爾来、歴代皇室の御尊崇も一層篤く、御祈願の御綸旨・院宣など縷々下賜せられました。武家の時代になってからも、崇敬を集め、国家安泰・武運長久の祈願のため、国司・探題等から社領、神田の寄付も度々ありました。戦乱のため社殿を焼失する事もあり、中でも大友氏の兵が当国に乱入の折、社殿と共に由緒などに関する古文書が兵火に罹りその多くは焼失しました。幸いに数十通の古文書類は残されたことで、その由緒を窺い知ることができています。
江戸時代になり、佐嘉藩祖の鍋島直茂、初代藩主の鍋島勝茂により再建されました。歴代藩主・鍋島家の崇敬神社として、毎年正月・5月・9月には、必ず藩主代拝の典儀がありました。大小祭典、並びに社殿営繕に要する一切の費用は、総て藩費の負担に属し、社地は3町歩、山林15町余、社禄物成38石、禀米30石が寄進されました。
明治3年(1870)には藩主鍋島直大の祖先累代の崇敬神社であった修理田村(現・佐賀市巨勢町修理田)の山王宮(日吉宮)を合祀したのを始めに、国史見在社の白角折神社(現在は旧地に復座)、及びその他無各社も合祀。社格制定では、当初は村社でしたが、大正5年(1916)6月26日に県社に昇格しました。
古くは農の神、酒の神様と敬われ、中世には医学の神様としても敬われました。古来、霊験著しく、霊妙不可思議なる御神徳を垂れ給うこと屡々であることから、佐賀・福岡の両県下に跨り崇敬されています。
境内には、樹齢800年や600年の楠の大木、モミジの古木を始め様々な針葉、広葉常緑樹、落葉樹が蒼然と繁り、四季の風光に富んでいます。参道中にある九年庵と共に新緑・紅葉の名所として広く知られ、見頃の期間は多くの参拝者で賑わいます。

「松尾宮」
大山咋命と中津島姫神を祀っています。古来より聖地として崇められていた当地に、天平元年(729)僧行基が、聖武天皇の勅願を賜り神殿を建立し、松尾明神を勧請。国土豊穣、国家安泰を御祈願されたのが創始です。広く酒の神様として知られ、醸造に纏わる神話が伝えられています。御祭神の大山咋命は、お猿が穀物を噛み(カミ)砕き、木の穴に入れているのを見ます。その後日、良き香りが漂い、お猿が口にしているのを目にします。不思議に思った大山咋命は、試しに飲んだところ美味しく、気持ちが良いことから自ら作るに至ったと伝えられています。これが酒の醸造の始まりとされ、大山咋命は酒の神様として崇敬されています。昔時は、当社でも猿酒として造られ頒布されていました。

「金剛水」
社殿後方から湧き出ている御神水。唐より帰朝した第3代天台座主の慈覚大師が、国家安泰を祈願の折、岩石に「水」と梵字を彫ると清らかな水が湧き、土の中から「日吉宮」と書かれた石額が掘出された伝えられています。山王さんの水として親しまれ、内臓(胃腸)弱き人は当神社の神符をこの清水と一緒に拝飲すれば神威増し回復に向かうとされています。また、初宮詣の子供の口につけ、長寿、無病息災を祈願する例となっています。御神水をじめとする境内には猿の像が数多く奉納されていますが、猿が「日吉宮(山王さん)」の眷属であるためです。金剛水のお猿さんに水をかけ願いをとなえれば叶えられるとされています。
「松森稲荷神社」
参道右手の小山に鎮座。倉稲魂神を祀っています。
「月夜見命」
社殿向かって左に奉斎されている石碑。月夜見命を祀っています。
「弁財天」
参道の放生池の畔に祀られています。
「下宮神社(十禅師)」
仁王門から県道21号を70mほど南に下って左手上に鎮座。御祭神は、大山咋神の母神である天知迦流比売命。大御田祭の折、本宮の大山咋神が、母神に会いに行く行幸が斎行され、一日滞在されます。天知迦流比売命は耳が悪く、大山咋神が3年に1度会いに行くというのを13年に1度と聞き間違え、親孝行の大山咋神はそれに反対せず、行幸は13年に1度になったと伝えられています。以前は、箒、火吹き筒が奉納されていました。
「御神木」
樹高約34.5m、根廻り7.2mのクスノキ。樹齢は800年以上とされ、神埼町天然記念物です。
「金剛力士像二体」
神埼市重要文化財。参道入口にある江戸時代建設の仁王門に安置されています。門は元々は、仁比山護国寺の山門であったと考えられ、三間一戸の八脚門の特徴を持っています。右に阿形、左に吽形の金剛力士(仁王)像で、九州でも最古級の仁王像とされています。戦乱中に焼失後、他から安置されたともいわれ、平安の流れがあり、鎌倉時代の作とされています。吽形が師匠作で、阿形がその弟子の作と考えられています。仁王門は、県遺産に指定されています。
式年大祭(大御田祭)
申年の4月初申より次申までの13日間執り行われる式年大祭で大御田祭と称されています。鎌倉幕府の成立した前後の建久年中(1190-1198)までは勅使が下向し、盛大に執り行われていました。以降は、肥前・筑前・筑後の三国より国造が交代で参向することとなりました。現在は、仮装の勅使を置いて、優待の格式が受け継がれています。祭りでは、佐賀県重要無形民俗文化財の御田舞が奉納されます。御田舞は、比叡山の日吉山王宮(日吉大社)の分霊を合祀したのを機に伝わったともされ、豊作を願う宮中での田楽を元であると考えられています。舞台2ヶ所、柱大きさ、数、床板の厚さ、床の高さ、階段、役者の員数年齢、役者決め、稽古始めなど総て慣習を守り引き継いでいます。歌、舞は期間を過ぎると一切行われず、門外不出です。昭和27年(1952)国無形文化財指定されますが、昭和29年(1954)文化財改正により解除。現在は、佐賀県重要文化財第1号に指定されています。