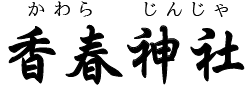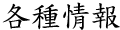辛国息長大姫大目命、忍骨命、豊比咩命を香春岳に祀る香春神社は、『延喜式神名帳』では名神小社に列格され、豊前国一宮とされた古社です。創祀は不詳ですが、社記『香春神社縁起』によれば、崇神天皇の御宇(BC97-BC30)、辛国息長大姫大目命、忍骨命の荒魂、豊比咩命の三柱の御神を香春岳に奉祀したのが創始とされています。
香春岳は南から一ノ岳(元491m・現在270m程)、二ノ岳(468m)、三ノ岳(511m)と並ぶ石灰岩からなる山で、元は草木の育たない石山であったとされています。その香春岳の三峰の各頂上に三柱の神霊を各々奉祀し、香春三所大明神と称し崇め奉ったとされています。
『豊前国風土記・逸文』によれば往古、鮎の泳ぐ清浄な川原(香春)を気に入った新羅国の神が住むに至ったのが香春大神(鹿春大神)となったとされています。
一ノ岳に祀られた辛国息長大姫大目命は、神代に新羅国に渡り、崇神天皇の御代に日本へ戻った神です。一ノ岳の山頂には周り36歩ばかりの沼があり、黄楊樹、及び龍骨があったと伝えられています。
二ノ岳に祀られた忍骨命(天忍穗耳尊)は、天照大神と素戔嗚尊の誓約で生まれた五皇子の第一皇子です。二ノ岳に祀られたのは忍骨命の荒魂で、その和魂は南山(一ノ岳)に祀られたとされ、二ノ岳の山頂には銅、黄楊樹、及び龍骨があったと伝えています。
三ノ岳に祀られた豊比咩命は、神武天皇の外祖母で住吉大明神の御母です。香春神社の祭礼の時だけ香春神社に坐し、祭礼が終わると宇佐宮放生会で神鏡を奉納した採銅所にある古宮八幡宮に帰社するとされています。三ノ岳の山頂には龍骨があったと伝えています。
『風土記・逸文』豊前國・鹿春郷
豐前國風土記曰 田河郡 鹿春鄕[在郡東北]此鄕之中有河 年魚在之 其源從郡東北杉阪山出 直指正西流下 湊會眞漏川焉 此河瀬淸淨 因號淸河原村 今謂鹿春鄕訛也 昔者 新羅國神 自度到來 住此河原 便卽 名曰鹿春神 又鄕北有峯 頂有沼[周卅六歩許]黃楊樹生 兼有龍骨 第二峯有銅竝黃楊龍骨等 第三峯有龍骨。
豊前国の風土記に曰はく、田河郡の鹿春郷(郡の東北に在り)。此の郷の中に河有り。年魚在り。其の源は、郡の東北のかた杉坂山より出でて、直ぐに正西を指して流れ下りて、真漏川に湊ひ会へり。此の河の瀬、清浄し。因りて清河原村と号けき。今、鹿春の郷と謂ふは訛れるなり。昔者、新羅の国の神、自ら度り到来りて、此の河原に住みき。便即ち、名づけて鹿春の神と曰ふ。又、郷の北に峯有り。頂に沼有り(周り三十六歩ばかりなり)。黄楊樹生ひ、兼、龍骨有り。第二の峯には銅、並びに黄楊・龍骨等有り。第三の峯には龍骨有り。
『續日本後紀』卷第六
承和四年十二月庚子(838年1月14日)。(略)太宰府言。管豐前國田河郡香春岑神。辛國息長大姬大目命。忍骨命。豐比咩命。惣是三社。元來是石山而上木惣無。
承和4年12月11日(838年1月14日)。(略)太宰府言う。管る豊前国田河郡の香春岑神、辛国息長大姬大目命・忍骨命・豊比咩命。総て是の三社は、元来是れ石山にして上に木総て無し。
建保元年(1213) 編纂の『彦山流記』によれば、中国の天台山にある王子晋の旧跡から来訪した彦山権現は、豊前国田河郡の大津村近くに船を着け、香春明神に宿を借りることを願います。しかし香春明神は、場所が狭く少ないことを理由に、宿を貸しませんでした。怒った彦山権現は、1万の眷属と10万の金剛童子に香春岳の樹木を引き抜かせてしまいました。そのため香春岳は、苔生す岩石ばかりの石山になってしまったと伝えています。
『彦山流記』建保元年(1213) 編纂
夫権現、(略)、甲寅歳震旦国天台山王子晋旧跡東漸、御意深凌西天之蒼波交東土之雲霞、其乗船舫親在豊前国田河郡有大津邑今号御舟是也。着岸之当初香春明神借宿、地主明神称狭少之由不奉借宿、爰権現発攀縁、勅壱万十万金剛童子、彼香春嶽樹木令曳取、因茲枝條蔽莀磐石露形。
夫れ権現、(略)、甲寅の歳、震旦国天台山の王子晋の旧跡より東漸す。御意の深さ西天の蒼波を凌ぎ、東土の雲霞と交わる。その乗りたる船を舫ふは豊前国田河郡大津邑の親くに在り。今、御舟と号すは是なり。着岸の当初、香春明神に宿を借る。地主明神、狭く少なし由と称し、借りの宿を奉らず。これに権現攀縁を発し、一万十万金剛童子に勅して、彼の香春嶽の樹木を曳き取らんと令ず。茲る枝を條ぎ蔽ふに因りて莀むす磐石の形を露わとす。
社記『香春神社縁起』によれば、和銅2年(709)一ノ岳南麓に一社を建立し、三神を合祀して香春宮と称したとされ、弘安10年(1287)に成立した社記『香春神社解文』では、その新宮に三神が合祀された際、日置絢子が三ノ岳の阿曾隈(採銅所)にて奉られていた豊比咩命も勧請されたと記しています。
延暦23年(804)桓武天皇より入唐求法の還学生に選ばれた最澄が、渡海の安全祈願のため香春神社へ詣でます。その仔細が、弘仁23年~元慶5年(822-881)の期間に編纂された『叡山大師伝』、及び正和2年(1313)に編纂された『八幡宇佐宮御託宣集』に記されています。
最澄は宇佐宮で渡海の安全を祈念したところ、八幡大神が示現し、新羅国から来住した香春大神は、新羅・大唐・百済の事を詳しく知っているので詣でるよう託宣します。最澄が香春社に赴くと、思いがけないことに、左の半身は人、右の半身は石の姿をした幽玄なる1人の僧が現われて「何者であるか」と問いただしました。最澄が宇佐宮での示現と神託を語ると、僧は自分こそがその語られた香春大神であると告げます。香春大神は最澄に、渡海の安全を守護するので、仏の慈悲、大悲の願海に浴して業道から救ってくれるよう頼んだのでした。
唐に渡った最澄は、天台山にて天台教学を受けて翌年の延暦24年(805)に帰朝します。しかし、その洋上で風波により船が沈みそうになります。最澄が安全を祈念すると八幡大菩薩が天童として虚空に現われ、香春大明神が碇石となって纜を結び、大竜となった竈門大菩薩は船を背に乗せて無事に岸へと辿り着き、心から神恩に感謝したのでした。そして最澄は、延暦25年(806)に天台宗を開いたのでした。
無事に帰朝した9年後の弘仁5年(814)の春、最澄は唐からの無事の帰朝と天台宗開創を奉謝し、当地を訪れ香春神宮寺を開きます。そして智顗(天台大師)による『法華玄義』・『法華文句』・『摩訶止観』、湛然(妙楽大師)による『法華玄義釈籤』・『法華文句記』・『止観輔行伝弘決』、及び『法華経』2部の書写を香春宮に納め、講読します。
最澄が神殿に向って、何事をもって神道と為すのか、どのように神恩への忠勤を果たすべきかを問うと、香春大神が示現して「我が在る所の山に、更に草木無し。法力を以て、若し生長せしめば、神の悦ぶ所なり」と宣りました。それを受けた最澄が『妙法蓮華経薬草喩品第五』を講読すると忽ちの内に、石山に草木が繁茂して森となり、山を覆ったとされています。
加えて『叡山大師伝』では、最澄の法音を聞いた香春大神は、久しく聞くことができなかった説法・読経を聞くことができたことを随喜したことを記しています。香春大神は説法・読経の謝礼として、斎殿を開き、自らが所持していた紫の袈裟と紫の衣を最澄に下賜しました。又、この講読の時、青空の下、香春岳に紫色に光り耀く雲が出て、辺りに靄が立ち込める瑞相が現われました。そのことを当地の郡司や刀彌等が最澄に奏上すると、最澄は弟子の義真に自らが亡くなるまでは、瑞雲が起ったことを秘するよう伝えました。最澄の没後に、この奇瑞があったことが知られるようになったと伝えています。
『叡山大師伝』弘仁23年~元慶5年(822-881)の期間に編纂
弘仁五年春。(略)又奉爲八幡大神。於神宮寺。自講法華敎。乃開講竟。大神託宣。我不聞法音。久歴歲年。幸値遇和上。得聞正敎。兼爲我修種種功德。至誠隨喜。何足謝德矣。苟有我所持法衣卽託宣主自開齋殿。手捧紫袈裟一紫衣一。奏上和上。大悲力故幸垂納受。是時禰宜祝等各歎異云。元來不見不聞如是奇事哉。此大神所旋法衣。今在山院也。又於賀春神宮寺。和上自講法華經。謝報神恩。是時豐前國田河郡司并村邑刀彌等。錄瑞雲狀。奏上大師。適取固封。告弟子義眞言。自非滅後。不得披封。奉敎固緘滅後披見。其文云。以今月十八日未時。紫雲光耀。自鹿春峰起。亙蒼空靄。覆講法之庭。忽見瑞相。擧衆歎異。郡解如別。昔大師。臨渡海時。路次寄宿田河郡賀春山下。夜夢。梵僧來到披衣。呈身而見。左半身似人。右半身如石。對和上云。我是賀春。伏乞和上。幸沐大悲之願海。早救業道之苦患。我當爲求法助晝夜守護。竟夜明旦。見彼山。右脇崩巖重沓。無有草木。宛如夢半身。卽便建法華院。講法華經。今呼賀春神功院是也。開講以後。其山崩巖之地。慚生草木。年年滋茂。村邑翁婆無不歎異。又託宣曰。海中急難時。我必助守護。若慾知我助。以現光爲驗。因玆毎急難時。有光相助。託宣有實。所求不虛。乃大師本願。始登山朝。終入滅夕。四恩之外。厚救神道。慈善根力。豈所不到哉。
弘仁五年の春。(略)又、八幡大神の為に奉る神宮寺に於いて、自ら法華教を講ず。乃ち開講を竟ると、大神託宣すらく。我法音を聞かずして、久く歳年を歴たり。幸に和上に値遇して正教を聞くことを得たり。兼て我が為めに種種の功徳に修するには至誠随喜す。何ぞ徳を謝するに足らん。苟も我が所持の法衣有り。即ち託宣の主、自ら斎殿を開きて、手に紫の袈裟一つ紫の衣一を捧げ和尚に奏上し、大悲力の故に幸に納受を垂れよと。是の時に禰宜・祝等、各歎異して云く。元より是の如き奇しき事を見ざる聞かざるかな。此の大神の施したまふ所の法衣、今山王院に在るなり。又、賀春神宮寺に於いて和上自ら法華経を講じて神恩を謝報す。是の時、豊前国田河の郡司、並びに村邑の刀彌等、瑞雲の状を録して大師奏上す。適ら取りて固く封じ、弟子の義真に告げて言く。自れの滅後に非ずんば。封を披くこと得ざれと。固く緘じて教へを奉つりて、滅後に披見す。其の文に云く、今月十八日未の時を以て。紫雲光耀して鹿春の峰より起り、蒼空に亘り、講法の庭に靄覆へり。忽に瑞相を見て、挙衆を挙げ歎異す。郡解、別の如し。昔大師、渡海に臨みし時、路次、田河郡賀春の山の下に寄宿す。夜の夢に梵僧来到して衣を披き、身を呈して見ゆ。左の半身は人に似、右の半身は石の如し。和上に対して云ふ。我は是れ賀春なり。伏して乞ふ和上。幸に大悲の願海に沐せしめて、早く業道の苦患を救ひたまへ。我れ当に求法の助けと為して、昼夜守護す。夜を竟へて明旦に彼の山を見るに、右脇は崩巌重沓して草木有ること無く、宛も夢の半身の如し。即便、法華院を建て、法華経を講ず。今、賀春神功院と呼ぶは是れなり。開講の以後、其の山の崩巌の地に慚く草木生して、年年滋茂せり。村邑の翁婆、歎異せざることなし。又託宣曰く、海中急難の時は、我れ必ず助け守護せん。若し我が助けを知らんと欲せば、光を現するを以て験と為す。因て玆れに急難の時毎に、光有り相ひ助く。託宣実有り。求る所、虚しからず。乃ち大師の本願は、登山の朝より始めて入滅の夕べに終るまで、四恩の外、厚く神道を救ひ給ふ。慈善根の力、豈に到らざる所あらんや。
『八幡宇佐宮御託宣集』大巻十一・又小倉山社部(上)
香春社流記云。伝教大師為祈申入唐事。延暦廿三年参宇佐宮。殊致精誠。奉増法楽之時。示現言。自此乾方香春云所霊験神令坐。新羅国神也。吾国来住。新羅。大唐。百済事能被鍳知。可信其教者。大師奉此神勅之間。詣彼社壇之処。不慮外有一僧。値途中。向吾言何人乎。奇此気色。語彼示現。僧言。我即此神也。大師造諸善而祈願。抽一心而請益。爰神令現之給。其片盤石片僧形也。星光之時如近而見物。明月之夜如遠而伺色。為幽々。為玄々。而神語云。八幡大菩薩阿登羅江。又法楽難忘。和上渡海在唐可守護也者。皈朝之時。於洋中有風波之難。依擬漂没祈念之間。大菩薩現天童在虚空。奉此厳詔。香春大明神成碇石。結纜竈門大菩薩成大竜負舟平安着岸。報寶心在。書写法花釈六十巻[天台。妙楽両大師釈]。法花経二部。奉納香春宮之上向神殿言。何事奉為神道。又可致忠勤耶。示現。我之在所山更无草木。以法力若令生長者。神之所悦也。大師講読妙法蓮花経薬草喩品之時。草木忽萠森列満山。大弐南渕長河朝臣感見此事。始奉寄水田十五町。永為之例。五ヶ任之間。已及七十五町而已。
香春社の流記に云く。伝教大師入唐の事を祈り申さんが為に、延暦廿三年、宇佐宮に参り、殊に精誠を致し、法楽に備へ奉る時、示現して言く。此より乾方の香春と云ふ所に、霊験の神坐まさしむ。新羅国の神なり。吾が国に来住す。新羅・大唐・百済の事を、能く鍳知せらる。其の教を信ずべしてへり。大師、此の神勅を奉る間、彼の社壇に詣る処に、不慮の外に一僧有り。途中に値ふ。吾に向つて、何人なるやと言ふ。此の気色を奇しみ、彼の示現を語る。僧の言く。我即ち此の神なり。大師諸善を造して祈願し、一心を抽んでて請益す。爰に神現れしめ給ふ。其の片は盤石にして、片は僧形なり。星光の時、近くして物を見るが如く、明月の夜、遠くして色を伺うが如し。幽々為り、玄々為り。しかるに神語つて云く。八幡大菩薩あとらへあり。又法楽忘れ難きなり。和上渡海して唐に在らば、守護すべきなりてへり。帰朝の時、洋中に於て、風波の難有り。依て漂没せんと擬す。祈念する間、大菩薩天童と現じて虚空に在り。此の厳詔を奉る。香春大明神は碇石と成りて纜を結び、竈門大菩薩は大竜と成りて舟を負ひ、平安にして岸に着く。報寶心に在り。法華釈六十巻[天台・妙楽大師の釈なり]を書経す。法華経二部を香春宮に納め奉る上、神殿に向つて言く。何事を神道と為し奉り、また忠勤を致すべきやと。示現して云く。我が在る所の山に、更に草木無し。法力を以て、若し生長せしめば、神の悦ぶ所なりと已上。大師妙法蓮華経薬草喩品を講読する時、草木忽に萠し、森列りて山に満つ。大弐南渕長河朝臣、此の事を感見し、始て水田十五町を寄せ奉り、永く例と為す。五ヶ任の間、已に七十五町に及ぶのみ。
『續日本後紀』卷第六
承和四年十二月庚子(838年1月14日)。(略)至延暦年中。遣唐請益僧最澄。躬到此山祈云。願縁神力。平得渡海。即於山下。爲神造寺讀經。爾來草木蓊鬱。神驗如在。毎有水旱疾疫之災。郡司百姓就之祈祷。必蒙感應。年登人壽異於他郡。望預官社。以表崇祠。許之。
承和4年12月11日(838年1月14日)。(略)延暦年中に至り、遣唐請益僧最澄、自ら此の山に到り、祈って曰く。願くは神力に縁って、平かに海を渡ることを得んと。即ち山下に於いて、神の為に寺を造り経を読む。爾来草木蓊鬱とし、神験在すが如し。水旱・疾疫の災有る毎に、郡司・百姓これに就て祈祷すれば、必ず感応を蒙る。年登り人寿ながきこと、他郡に異なり。望むらくは官社に預かり、以て崇祠を表さんと。これを許す。
承和10年(843)3月3日、辛国息長大姫大目命、忍骨命が、正一位の神位に叙せられます。『日本三代実録』の貞観13年(871)2月26日条では、従五位上であった辛国息長大姫大目命と忍骨命に従四位上の神階が授与されたことが記されています。延長5年(927)に編纂された『延喜式神名帳』では、豊前国の名神小社とされました。
『日本三代實録』卷第十
貞觀七年二月廿七日(865年4月1日)。豐前國從五位上辛國息長比咩神。忍骨神。並授從四位上。
『延喜式神名帳』延長5年(927)編纂
豐前國六座。大三座・小三座]。宇佐郡三座[竝大]、八幡大菩薩宇佐宮[名神大]、比賣神社[名神大]、大帶姬廟神社[名神大]。田川郡三座[竝小]、辛國息長大姬大目命神社[名神小]、忍骨命神社[名神小]、豐比咩命神社[名神小]。
『香春社解状』、及び『大宮司申状写』の伝えるに永承年中(1046-1053)天台座主西明坊の時、造営遷宮之儀式が置かれ、以後建暦年中(1211-1213)まで、6度退転なく行われます。 建仁元年(1201)には豊比咩命が正二位に奉られ、建暦2年(1212)8月21日には「香春明神は聖朝鎮護無雙の霊神である故、33年毎に造営するよう宣旨がなされます。寛元元年(1243)10月8日の宣旨では、当社の造営は、朝家の経営、当国の課役となすとされ、歴代皇室の御尊崇の厚さを伝えています。
文永5年12月16日(1269年1月26日)に類火により炎上し、天台宗の第7祖とされる道邃の金泥妙典、最澄の直筆、寛元元年(1243)に造営を命じた宣旨、住吉大神の神宝、文書などの宝物を焼失。正応元年(1288)に少弐氏により再建。その後にの戦乱の中、盛衰を経ますが天正14年(1586)豊臣秀吉の九州平定の際、社領没収により神宮寺の僧は離散し、宮司・神官の権威は失墜します。江戸期中期になり、元禄16年(1703)の小笠原藩の社禄の寄付等により社勢を回復し、延享2年(1745)に社殿を再建しました。
明治4年(1871)9月郷社に列格して香春神社と改称。明治6年(1873)7月15日県社に列せられました。大正4年(1915)1月14日に神饌幣帛料供進社に指定されました。建築物として鳥居や手洗盤などは江戸初期であるものの、本殿などは文化・文政期(1804-1830)に改築されたものです。西側の回廊は、平成期の改築。本殿一棟、拝殿一棟、東側の回廊一棟、石垣は香春町第18号文化財指定を受けています。
社殿向かって右手に奥に宇迦之御魂神を祀る白八稲荷大明神。その手前には、昭和14年(1939)6月30日の午後3時頃、一ノ岳の採石場から神社後方の山林を突破して回廊前に転落した巨岩「山王石」が祀られています。その大きさは高さ4m20cm、周囲約15.6m、重さ約86t。東回廊の隅柱を損傷しただけで、ほとんど被害がありませんでした。これは神様のおかげであるとされ、山頂の山王神社にちなんで「山王石」と命名され、神の宿る石として祀られています。
社殿向かって左手前に石祠の三社。右手より蛭子社。諏訪社。天福社です。
社殿奥、本殿向かって左手に鎮座するのは、明治34年(1901)に香春岳一ノ岳山頂に建立され、昭和34年(1959)3月3日に遷座建立された納神社です。
【一ノ岳、石灰岩採掘の経緯】
明治21年(1888)旧香春町と旧下香春村と合併した香春町は、農業を主業として営むも、交通の要衝、近隣の中心地として栄えた町でした。しかし、筑豊炭田が大きな産業となるのに合わせ、石炭の採掘の少ない香春から町の中心地は離れることとなりました。農村の不況、並びに商工業の衰退により香春町は年々活気を失います。その中、町の財政の出費は嵩むこととなっていました。
その中で昭和6年(1931)8月、町長の江本達雄氏は、香春町の部落有林野が旧下香春村の所有に属し、香春岳の一ノ岳、二ノ岳、及び三ノ岳の南半面から、採銅所村、旧金川村に跨る広さに達し、香春町の林野面積の約7割を占めることに着目します。
化学肥料の利用増加と農業の副業化。秣や薪炭の採取も減少して未利用地も多かったことから、町を挙げて香春町の管理に一元化して収益の集約を計り、町財政の基礎を確立させようと動きます。昭和7年(1932)3月18日委員会の協定を遂げ、3月21日には町会で満場一致の可決をなして、60余歩町の県行造林実施を見るに至りました。
しかし、石炭の採掘も僅少で、狭溢とした土地である香春町は、各種施設の運営や教育の充実に備える財源は乏しく、町の財政は厳しいものがありました。また、この時期は昭和5-6年(1930-31)の昭和恐慌が発生していた時期でもありました。
その昭和恐慌から急速に経済回復を遂げていた昭和8年(1933)6月に浅野セメント株式会社の香春工場誘致の話が持ち上がります。香春町では直ちに期成同盟会が結成され、工場誘致の実現へ動く中、木村健吉氏が町長に就任します。
町として有力な産業の無い香春町は、石灰岩でできた香春岳の一部を犠牲として、発展を計ることが最も適切な策とされ、町会議員、町民代表と協議を重ね、その結論を実施することを決します。浅野セメント株式会社とも折衝を重ねた結果、町を挙げての誘致が決まり、同年11月に浅野セメント株式会社会社との協定が成立。同年11月21日に町会に議案が提案され、満場一致で可決。直ちに県知事へ林野処分の要請がなされ、昭和9年(1934)6月22日付をもって許可されました。
昭和10年(1935)6月に工場が開設され、製造が始まります。それ以降も数回に及ぶ増設と山の買収が行われ、香春町の主要産業となったのでした。当初はセメント用材として採掘されていましたが、現在は非常に純度の高い「香春岳寒水石」の産地として知られています。
※この項は、「香春町誌編集委員会編『香春町誌』香春町, 昭和41年 [p106-107]:誘致の理由」を元に紹介させていただきました。